寝ない子供を寝かせるコツは?寝ない理由は?年齢別原因と対策
子供が寝ないことは、子育て中のママにとって大きな悩みの1つですよね。
成長のためにもよく寝る子になってほしいものの、子供が寝ない原因は大人にある場合もあります。
寝ない子供を上手に寝かせるコツや年齢別の原因と対策を知り、子供が上手に寝られるようサポートしてあげましょう。
目次
- なかなか寝ない子供を、よく寝る子に導く3つの基本
- 家族の1日の生活リズムの見直し
- 運動不足の解消
- 夜・睡眠前の習慣の見直し
- 赤ちゃんが寝ない…原因と対策、夜泣きとの関係
- 赤ちゃんの睡眠サイクルは大人とは違う
- 睡眠環境を見直す
- 1歳・2歳、寝ない原因は?理想の睡眠時間は?
- 1歳・2歳の理想の睡眠
- 寝られないなら夜の授乳を見直す
- 昼間のイヤイヤが睡眠に影響している場合も
- 【幼児】3歳・4歳・5歳が寝ない原因は?理想の睡眠時間は?
- 3歳〜5歳の理想の睡眠時間
- お昼寝しすぎが原因?!生活を改めて見直そう
- 【小学生(6歳以降)】寝ない原因は?理想の睡眠時間は?
- 小学生の理想の睡眠時間
- だらだら夜更かししない意識付けを
- 寝ない子は「早起き」の習慣から
- 寝ないのは、ママ・パパの帰宅時間
- 日本の睡眠の現状
- 3歳以下の睡眠時間も短い
- 子供の夜ふかし、親の生活習慣の影響も
- 子供が寝ない原因チェックリスト
- これって睡眠障害?4つのチェックポイント
- 寝ない子供とよく寝る子供の違い
- 体内時計が整っているか
- 身体を動かしているか
- 毎日決まった時間に布団に入る
- まとめ
なかなか寝ない子供を、よく寝る子に導く3つの基本
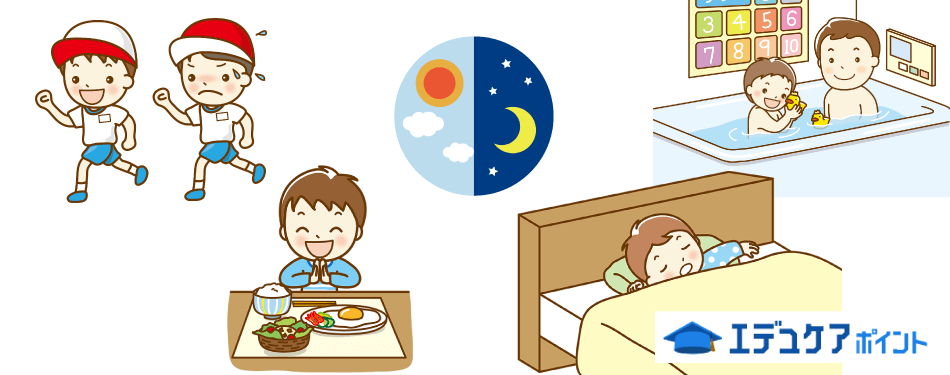
子供がなかなか寝てくれないと、イライラが募りますよね。
よく寝る子になるには、親子で生活リズムを整えるのがカギです。
よく寝られるようになる3つのポイントを解説します。
【子供が寝ないときの見直しポイント】
- 家族の1日の生活リズムの見直し
- 運動不足の解消
- 夜・睡眠前の習慣の見直し
家族の1日の生活リズムの見直し
子供の生活習慣は親の行動に影響を受けます。
親が夜型生活を送っていると、子供の生活も夜型にならざるを得ません。
親の職業によっては完璧な解決が難しい場合もありますが、可能な限りで家族全員の生活リズムを見直していきましょう。
まず見直したいのは、朝の過ごし方です。
朝は親も子も一緒に起きて、窓を開けて太陽の光を直接感じたり、カーテンを開けて部屋の中に朝の光を取り込んだりします。
体内時計は朝の太陽の光を浴びることでリセットされ、そこから約14時間後から少しずつ眠気を感じるようになります。※1
例えば、朝7時に太陽の光を浴びると、夜9時には自然な眠気が巡ってくるのです。
これを家族の習慣にしていきましょう。
朝の習慣は、平日は続けやすいものの、週末は親が遅くまで寝てしまいがちです。
「休日くらいのんびり寝坊したい」という気持ちにもなりますが、週末に睡眠のリズムが崩れると親も子も月曜日の朝に起きづらくなってしまいます。
早起きして光を浴びる習慣は、平日だけでなく週末も大きく崩さずに続けましょう。
運動不足の解消
子供と向き合う中で「運動させると子供がよく寝る」と実感しているパパやママも多いのではないでしょうか?
絵本を読んだり、歌を歌ったりしても子供が眠らないのは、日中の運動不足が関係しているのかもしれません。
運動する習慣があると、寝つきがいいばかりか、質のいい睡眠がとれることが様々な研究からわかっています。※2
天気のいい日は、子供を公園などに連れて行き思いきり遊ばせてあげましょう。
適度な疲れが夜の眠気につながりやすくなります。
さらに子供が「パパやママと一緒にたくさん遊んだ」という充実感も、子供の睡眠には有効です。
雨の日など外にでかけられない日は、室内でダンスや体操など、体を動かす遊びを取り入れてみてはいかがでしょうか。
夜・睡眠前の習慣の見直し
子供の睡眠時間から、毎日の起きる時間と寝る時間の目標を決めたら、夜の過ごし方も見直します。
家族は子供の入眠や眠りを妨げないよう、気にしてあげるとよいでしょう。
強い光を発するテレビやパソコンを控える、スマホは子供が勝手に触れない場所に置くなどの工夫を。
子供の体内時計は夜の光に影響を受けやすく、テレビやスマホなどの光は大人が実感する以上に睡眠の邪魔になっています。
特に、寝る前にスマホで動画などを見せている場合は要注意です。
子供は画面の光を大人よりも近い距離で見ていて、約2倍も明るい光を浴びていることが指摘されています。※3
寝かしつけは動画を見せずに、絵本を読むなど他の方法に切り替えましょう。
子供のスマホとゲームへの向き合い方については、下記記事で詳しく解説しています。
子どもとスマホの付き合い方。ルールや制限の仕方とは?
次章からは、年齢別に子供が寝ない原因と対策をご紹介します。
※1:厚生労働省 e- ヘルスネット「子どもの睡眠」/2021年5月13日現在
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/heart/k-02-007.html
※2:厚生労働省 e- ヘルスネット「快眠と生活習慣」/2021年5月13日現在
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/heart/k-01-004.html
※3:厚生労働科学研究費補助金 未就学児の睡眠・情報通信機器使用研究班「未就学児のための睡眠Q& A保護者の方へ 」/2021年5月13日現在
http://childsleep.org/guideline/wp-content/uploads/%E7%9D%A1%E7%9C%A0QA-%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E8%80%85%E3%81%AE%E6%96%B9%E3%81%B8.pdf
赤ちゃんが寝ない…原因と対策、夜泣きとの関係
赤ちゃんの睡眠サイクルは大人とは違う
の記事で解説の通り、赤ちゃんの睡眠サイクルは大人とは異なります。
生まれたての赤ちゃんは1~4時間眠っては1~2時間起きているというサイクルで眠ります。※4
赤ちゃんは大人よりも短い睡眠サイクルを繰り返すため、何度も目を覚ますのです。
3~6歳ごろには赤ちゃんの睡眠サイクルが大人と同じ脳波になり、5歳前後には昼寝をとらない子も増えます。※4
1歳までの赤ちゃんの時期は、発達段階にあわせた睡眠時間を参考に、生活リズムを整えていきましょう。
赤ちゃんの寝かしつけのコツは?【月齢別】楽に寝かしつけられる方法
では、具体的な生活リズムの整え方をご紹介しています。
睡眠環境を見直す
赤ちゃんが寝てくれないときは、睡眠環境が整っていないのかもしれません。
大人には気にならないようなことでも、赤ちゃんにとっては不快なこともあります。
下記を参考に、環境を見直してみてください。
- 暑すぎたり寒すぎたりしないか※5
- エアコンの風などがあたらないか※5
- 部屋が明るすぎないか※5
- うるさくないか※5
- 夜中の授乳やおむつ替えのとき部屋を明るくしていないか※5
赤ちゃんの睡眠環境については、
赤ちゃんにはベッド?お布団?安全な寝室の環境と夏冬の布団対策
こちらの記事で詳しくご紹介していますので、併せて参考にしてみてください。
※4:厚生労働省 :未就学児の睡眠指針/2021年5月13日現在
https://www.mhlw.go.jp/content/000375711.pdf
※5:夜泣き予防プロジェクト ママと赤ちゃんが夜よく眠れるように ベビー睡眠編 /監修 久保田俊郎/東京医科歯科大学産婦人科教授/2021年5月13日現在
https://www.jpm1960.org/pdf/kosodate_pdf4.pdf
1歳・2歳、寝ない原因は?理想の睡眠時間は?
1歳・2歳の理想の睡眠
赤ちゃんの頃は昼間もよく眠りますが、1歳になると1日の睡眠時間の大半を夜まとめてとれるようになります。
お昼寝は1回、1.5~3.5時間くらい。※4
1日の平均的な総睡眠時間は11~12時間程度にまで減ります。※4
この年代で身につけたい睡眠習慣は、
- 寝る時間と起きる時間が規則正しいこと
- 夜8~9時頃までには眠りについて朝7時頃には自発的に起きられる
- 昼は長い時間起きていて夜は朝まで眠り続けること
この3つです。
寝られないなら夜の授乳を見直す
子供が「夜にまとまった睡眠がとれていない」とお悩みの家庭では、ママが横になったままで授乳する「添い乳」が睡眠を妨げる原因になっていることもあります。※6
添い乳がないと寝られない子供もいるため、やめ時の判断が難しいと感じるママも少なくありません。
しかし、添い乳の習慣があり子供が夜の睡眠リズムを崩している場合は、タイミングをみて断乳を検討してもよいかもしれません。※6
昼間のイヤイヤが睡眠に影響している場合も
2歳前後になると子供も自己主張が激しくなり、イヤイヤ期がはじまります。
イヤイヤ期には一時的に夜泣きをすることも。
昼間、自分が納得できない気持ちを抱えて過ごすと、夜もその気持ちを引きずり夜泣きに繋がっているのです。
しかし、これは成長の一段階です。
成長とともにおさまるので心配いらない場合が多いようです。
この頃の夜泣きについては、
赤ちゃんの夜泣きいつからいつまで?月齢で違う原因と対策でつらさを乗り切る
こちらの記事で詳しくご紹介しています。
※4:厚生労働省:未就学児の睡眠指針/2021年5月13日現在
https://www.mhlw.go.jp/content/000375711.pdf
※6:子どもの夜ふかし 脳への脅威 三池輝久著 集英社新書 2014年8月発行
https://shinsho.shueisha.co.jp/kikan/0735-i/
【幼児】3歳・4歳・5歳が寝ない原因は?理想の睡眠時間は?
3歳〜5歳の理想の睡眠時間
3歳を過ぎた子供は睡眠のリズムが安定し、昼寝をとらない子も出てくる時期です。※4
3~6歳の子供の1日の平均的な睡眠時間の目安は11~12時間程度。※4
夜まとまって寝られるようになります。
お昼寝しすぎが原因?!生活を改めて見直そう
3歳~5歳頃になると、お昼寝は1~2時間とれば十分です。※1
5歳頃になれば、お昼寝しなくても、夜まで元気に過ごせる子もいるでしょう。
1歳~2歳の頃のお昼寝習慣をそのままにしていると、3歳~5歳児にはお昼寝が長すぎます。
お昼寝しすぎると夜寝るのが遅くなりますので、1時間くらいで一度起こしてみてもよいかもしれません。
さらに、お風呂に入る時間も寝つきに関係します。
お風呂から上がってすぐは、体が温まりすぎていて寝られないものです。
お風呂を上がってから寝るまでの時間が短い場合には、お風呂の時間を見直してみると寝付くのが早くなるかもしれません。
※4:厚生労働省:未就学児の睡眠指針/2021年5月13日現在
https://www.mhlw.go.jp/content/000375711.pdf
※6:子どもの夜ふかし 脳への脅威 三池輝久著 集英社新書 2014年8月発行
https://shinsho.shueisha.co.jp/kikan/0735-i/
【小学生(6歳以降)】寝ない原因は?理想の睡眠時間は?
小学生の理想の睡眠時間
小学生になるとお昼寝はせず、1日9時間~11時間くらい睡眠を取るのが理想です。※4
しかし、小学生の睡眠時間は短く、世界の小学生と比較しても夜更かしをしがちなことが分かっています。※4
だらだら夜更かししない意識付けを
寝る前にテレビやゲームをやると、不要な明るい光を浴びてしまい寝つきが悪くなります。
テレビやゲームの睡眠への影響は問題視されていますが、それよりも「なんとなく夜更かしをしている」子の方が多いと言われています。※4
家族の生活習慣の影響も考えられますが、子供本人に「だらだらと夜更かしをすることがよいことではない」ことを教え、寝る時間になったらベッドに入るなど、すべき時間と行動を習慣づけていきましょう。
寝ない子は「早起き」の習慣から
早く寝ることを意識するよりも、早く起きることを意識するようにしましょう。
朝、日の光を浴び、朝ごはんを食べることで体内時計が整います。※1
小学生になったら朝早めに起こして、しっかり朝ごはんを食べる習慣づけが肝心です。
早起きを習慣化できれば、朝の時間を活用して勉強もできますよね。
朝は、脳科学的に見ても、新しい記憶を脳にインプットしたり考え事をしたりするのにはピッタリの時間帯だと言われています。
は他にもいくつかありますので、こちらの記事を参考にしてみてください。
※1:厚生労働省 e- ヘルスネット「子どもの睡眠」/2021年5月13日現在
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/heart/k-02-007.html
※4:厚生労働省:未就学児の睡眠指針/2021年5月13日現在
https://www.mhlw.go.jp/content/000375711.pdf
寝ないのは、ママ・パパの帰宅時間
「うちの子はどうして寝ないのだろう…」と思ったら、子供だけでなく大人の生活にも注目してみてください。
日本の睡眠の現状
あなたは毎日、何時間眠れていますか?
日々の生活で、あまり眠れていないと実感している大人も多いのではないでしょうか?
日々のわずかな睡眠不足が借金のように積み上がっている現象は「睡眠負債」とも呼ばれています。
厚生労働省が令和2年に実施した調査によると、日本人の1日の平均睡眠時間は「6時間以上7時間未満」が最も高い割合で、男性 32.7%、女性 36.2%です。※7
ただ「6時間未満」をまとめると、男性 37.5%、女性 40.6%と、4割前後の人は睡眠時間が6時間未満となっています。※7
さらに、日本人の睡眠は、世界各国と比較しても短いことが明らかになっています。
経済協力開発機構(OECD)の2018年の調査によると、日本人の平均睡眠時間は442分(7時間22分)でした。※8
これは調査対象の30カ国の中で最下位です。※8
3歳以下の睡眠時間も短い
また、日本人の睡眠時間が短いのは、大人だけの話ではありません。
日本は大人だけでなく子供も睡眠時間が短いのです。
3歳以下の子供の1日の総睡眠時間を、世界の国々の同年代の子供と比べてみたデータがあります。
それによると、日本の乳幼児の1日の総睡眠時間は11.62時間で、調査対象の17の国と地域の中で最も短くなっています。※9
最も長いのはニュージランドで、日本との差は2.3時間。※9
毎日の睡眠時間に2時間もの差があるのです。
子供の夜ふかし、親の生活習慣の影響も
では、なぜ日本の子供の睡眠時間が短いのでしょうか?
最大の原因は、親子の「夜更かし」です。
子供は、大人と比べ必要な睡眠時間が長いですよね。
子供が親より先に布団に入りすんなり寝られればよい ものの、親が寝かしつける習慣が続いていると、なかなか子供も一人では寝られないものです。※4
また親子同じ寝室で寝る習慣の場合、親の睡眠習慣が子供に影響すると懸念されています。※4
・ママの働く時間が長いほど子供の寝る時間が遅い
現代は女性の社会進出が増えて共働きの家庭が多くなり、長時間労働も当たり前になっています。
パパもママも遅くまで働いていると帰宅時間も遅く、どうしても子供の生活も夜型になりがちですよね。
実際にある調査では、ママの仕事の終わりが遅いほど、22時以降に寝る子の割合が増えることがわかっています。※1
・パパの帰宅時間にも注意を
ママだけでなくパパの帰宅時間も子供が寝ない原因の1つになっている可能性もあります。
子供が寝る時間の前後にパパが帰宅して、子供の眠気がとんでしまった経験はありませんか?
一度眠りについた子供が覚醒すると、夜のまとまった眠りが分断されてしまいます。
就寝時間を過ぎていたら子供を起こさないようパパの協力も必要です。
子供が寝ない原因は、家庭環境により他の要因も考えられます。
寝ない子供の寝かしつけのコツ
こちらの記事で、いくつかの原因をご紹介しています。
※1:厚生労働省 e- ヘルスネット「子どもの睡眠」/2021年5月13日現在
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/heart/k-02-007.html
※4:厚生労働省:未就学児の睡眠指針/2021年5月13日現在
https://www.mhlw.go.jp/content/000375711.pdf
※7:厚生労働省 令和元年 国民健康・栄養調査結果の概要 /2021年5月13日現在
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000687163.pdf
※8:OECD Balancing paid work, unpaid work and leisure /2021年5月13日現在
https://www.oecd.org/gender/balancing-paid-work-unpaid-work-and-leisure.htm
※9:乳幼児の睡眠と発達/岡田(有竹)清夏/2021年5月13日現在
https://www.jstage.jst.go.jp/article/sjpr/60/3/60_216/_pdf
子供が寝ない原因チェックリスト
寝ない子供に悩む家庭では、こんなことが起こっていませんか?
【子供が寝ないときのチェックリスト】
- 寝かしつけに2~3時間かかる
- 寝る準備を始めても子供が「まだ寝ない」と抵抗する
- 興奮している、テンションが高い
- 絵本を何冊も読まないと寝ない
- 「遊びたい」と言って、おもちゃを出したり動画・DVDを見せたりしないと気が済まない
- ママが先に寝ようとすると怒る
- 布団を出て歩き回ったり、ゴロゴロしたりする
- 子供が眠ってからママが離れると泣いたり、探しに来たりする
2歳前後から訪れるいわゆる「イヤイヤ期」は、自我が芽生えてやりたいことが増えていく一方、欲求を抑制する脳の前頭前野が未熟なため我慢ができません。
多くのママが、寝かしつけに困る時期の1つです。
イヤイヤ期自体は子供の成長において大切な過程の一つ。
「育て方が悪かったのかしら…」と過度に心配する必要はありません。
詳しくは、
で解説しています。
これって睡眠障害?4つのチェックポイント
あまりに寝てくれないと、「うちの子が寝ないのは本当に大丈夫?」と気になりますよね。
厚生労働省の調査によると、2%の子供が睡眠時無呼吸症候群だとも言われています。※1
睡眠習慣を整えても寝られない場合は、下記を参考に子供を観察してみてください。
【寝られない子供の観察ポイント】
- 寝ている途中に呼吸が止まっていないか※1
- 眠りの質が悪くないか※1
- 寝つきや寝ているときに身体に異常な動きがないか※1
- 日中、眠気が強くないか※1
これらが1ヶ月以上続くと、受診の目安とされています。※1
子供が睡眠障害かどうかを正確に知るには、上記のチェックポイントだけで自己判断せず、小児科医の診察を受けましょう。
※1:厚生労働省 e- ヘルスネット「子どもの睡眠」/2021年5月13日現在
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/heart/k-02-007.html
寝ない子供とよく寝る子供の違い
体内時計が整っているか
寝ない子供とよく寝る子供の違いは、「体内時計」というキーワードにあります。
寝ない子供は「体内時計」と実際の生活が合っていないと言われています。
体内時計とは、体温調整、ホルモンの分泌など生きていくために必要なあらゆる体の機能を調節している脳の働きのこと。
睡眠のリズムもコントロールしています。
1日は24時間ですが、人間の体内時計は、24時間よりも少し長い(一部の人は24時間より少し短い)ことが分かっています。※2
このため、24時間のリズムに合わせるためには体内時計のリセットが必要なのです。※2
最も効果的な方法は、朝にカーテンを開けて太陽の光を浴びることです。※2
身体を動かしているか
習慣的に運動している方が、寝つきがよいと言われています。※2
激しい運動は逆効果ですので、適度に身体を動かすのがちょうどいいようです。※2
小学生になると体を動かす時間が減りますが、下校後などに外遊びの時間を作りましょう。
毎日決まった時間に布団に入る
規則正しい生活は、よい睡眠には欠かせません。
決まった時間に布団に入り、朝は早めに起きることで生活リズムが整います。※2
また朝ごはんをしっかり食べないと、夜の睡眠にも影響すると言われています。※2
親子で朝ごはんを摂る習慣を身につけましょう。
※2:厚生労働省 e- ヘルスネット「快眠と生活習慣」/2021年5月13日現在
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/heart/k-01-004.html
まとめ
子供が寝ないのは、家庭の生活習慣が原因の可能性もあります。
成長とともに子供の生活サイクルは変わることもありますが、親が変化に対応できていないと子供が寝ない原因にもなります。
授乳やお昼寝時間、お風呂やごはんの時間というような1日の流れを赤ちゃんの成長に合わせてアップデートしていきましょう。
近年、テレビやゲーム、スマホの子供の睡眠への影響が指摘されています。
親子でルールを決めて使用し、寝る前は極力控えましょう。
しかし、テレビやゲームよりも、だらだらと夜更かしをしてしまうことで夜型の生活になり、寝られないことが多いことがわかっています。
子供とよく話をして、夜更かしは成長にとって良くないということ、早起きの習慣をつけるメリットなどを伝えていきましょう。
適切な睡眠がとれるようになれば、目覚めも良くなり、親も子も気持ちのよい一日のスタートを切ることができるようになります。
できることから実践して、子供に合った方法を探してみてくださいね。




